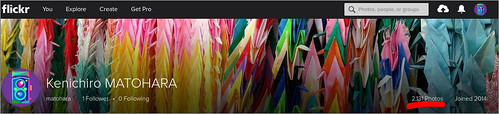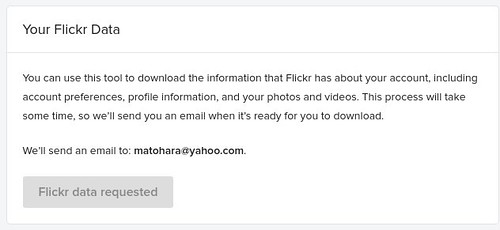Raspberry Pi model A/A+/Zero/ZeroW/ZeroHW/Compute Module/Compute module 3ではUSB-OTGが利用できます.(ZeroHW/Compute Module/Compute module 3は自分は未確認)
USB-OTGでUSBをEthernetにしてHostPCからアクセスするようにするとUSBケーブル1本で電源と併用できて便利です.
このときMACアドレスはモジュール読み込み毎に自動生成されます.
以下の例では,接続先(PC等)から見えるMACが HOST MAC 6a:b3:b1:5e:22:89 で,Raspberry Pi の中でのMACが MAC ae:3a:c7:8e:50:38 になっています.
$ sudo modprobe g_ether
$ dmesg | tail -15
[ 88.517568] using random self ethernet address
[ 88.517590] using random host ethernet address
[ 88.519210] usb0: HOST MAC 6a:b3:b1:5e:22:89
[ 88.520195] usb0: MAC ae:3a:c7:8e:50:38
[ 88.520396] using random self ethernet address
[ 88.520412] using random host ethernet address
[ 88.520534] g_ether gadget: Ethernet Gadget, version: Memorial Day 2008
[ 88.520546] g_ether gadget: g_ether ready
[ 88.520580] dwc2 20980000.usb: bound driver g_ether
[ 88.866651] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): usb0: link is not ready
[ 94.048758] dwc2 20980000.usb: new device is high-speed
[ 94.128837] dwc2 20980000.usb: new device is high-speed
[ 94.197523] dwc2 20980000.usb: new address 9
[ 96.057234] g_ether gadget: high-speed config #1: CDC Ethernet (ECM)
[ 96.095719] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): usb0: link becomes ready
$ /sbin/ifconfig usb0
usb0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.42.0.212 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.42.0.255
inet6 fe80::5855:ab0c:6628:557c prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether ae:3a:c7:8e:50:38 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 208 bytes 17243 (16.8 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 67 bytes 7696 (7.5 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0これは毎回変わるのでふと気づくとホストPCのネットワークの設定が沢山になっていたり…….
$ nmcli connection show | grep ethernet | wc -l 25
MAC addressを固定するにはモジュール読み込み時に指定してあげればOKです.
$ sudo rmmod g_ether $ sudo modprobe g_ether host_addr=de:ad:fe:ef:00:01 dev_addr=de:ad:fe:ef:00:00 $ dmesg | egrep usb0:.*MAC | tail -2 [ 1067.248443] usb0: HOST MAC de:ad:fe:ef:00:01 [ 1067.248958] usb0: MAC de:ad:fe:ef:00:00
永続化するには,g_etherモジュールを読んでいるところで指定してあげます.
modules-load=dwc2,g_cdc g_ether.host_addr=de:ad:fe:ef:00:01 g_ether.dev_addr=de:ad:fe:ef:00:00
g_ether g_ether.host_addr=de:ad:fe:ef:00:01 g_ether.dev_addr=de:ad:fe:ef:00:00
Note | ※g_cdcの場合はこんな感じで
|
modprobe g_ether host_addr=de:ad:fe:ef:00:01 dev_addr=de:ad:fe:ef:00:00
このときのMAC addressは g_ether が自動生成したものを使うのが無難だとおもうのですが,ランダムとかでいんだろうか?という不安があります.
ベンダーIDに使われていない領域だったら多分問題ないですが,これから埋まることもありそうです.(IPアドレスのプライベートIPアドレスのような領域があるのかもしれ無いけど未確認)
Raspberry Pi model B シリーズのNICには Raspberry Pi Foundation のベンダーコードが使われています.
$ grep -i raspberry /usr/share/nmap/nmap-mac-prefixes B827EB Raspberry Pi Foundation
Raspberry Pi の smsc95xx の MAC address の生成は,上6桁はベンダーIDの b8:27:eb を,下6桁はボードのserialの下6桁を割り当てているようです.
MAC address generation
To have a predetermined MAC address, a given SMSC LAN9512 must be attached to an EEPROM that contains the MAC address. But on the Raspberry Pi Model B, this EEPROM is not present; therefore, this driver must assign a MAC address itself. We do this by generating a MAC address from the board’s serial number. This guarantees that a given Raspberry Pi will always have the same MAC address and that two Raspberry Pis are extremely unlikely to be assigned the same MAC address.
手元の Raspberry Pi 2 Model B を確認すると確かにそうなっているようです.
$ ifconfig | grep ether ether b8:27:eb:ff:56:0a txqueuelen 1000 (Ethernet) $ grep Serial /proc/cpuinfo Serial : 0000000094ff560a $ sed -n "s/^Serial.*:.*\(..\)\(..\)\(..\)$/b8:27:eb:\1:\2:\3/p" /proc/cpuinfo b8:27:eb:ff:56:0a $ cat /proc/device-tree/model ;echo Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
Note | 16進数6桁は 0xFFFFFF → 16777215です,Raspberry Pi は2018年3月時点で190万台出荷しているようなので2周目に入っています.低い確率でしょうが同じMAC addressが割り当てられる可能性が…….
内蔵ネットワークに自分でMAC addressを指定したい場合はこんな感じでいけます. /boot/cmdline.txt に以下を設定 smsc95xx.macaddr=b8:27:eb:00:00:00 /etc/network/interfaces でも設定できるはずだがRaspbianでは未確認 hwaddress ether b8:27:eb:00:00:00 CPU Serialを詐称する手も? |
ということで,Raspberry Pi model A / Zero でもこの MAC address が利用できそうな感じです.外向けの HOST MAC をこのアドレスにしてみます.
$ sed -n "s/^Serial.*:.*\(..\)\(..\)\(..\)$/b8:27:eb:\1:\2:\3/p" /proc/cpuinfo | tee ~/macaddress b8:27:eb:d8:63:18 $ sudo vi /boot/cmdline.txt $ sudo reboot : : $ dmesg | grep usb0 [ 4.937660] usb0: HOST MAC b8:27:eb:d8:63:18 [ 4.937845] usb0: MAC 86:d7:fe:57:f2:d5
ホストPCでもちゃんと指定したものになっています.
$ /sbin/ifconfig enxb827ebd86318 | grep ether ether b8:27:eb:d8:63:18 txqueuelen 1000 (Ethernet)
とりあえずこれで使ってみようと思います.
$ lsb_release -d Description: Raspbian GNU/Linux 9.4 (stretch) $ uname -m armv6l $ cat /proc/device-tree/model ;echo Raspberry Pi Model A Rev 2